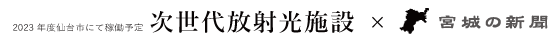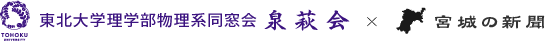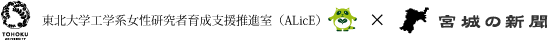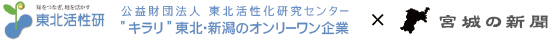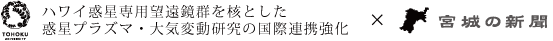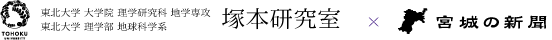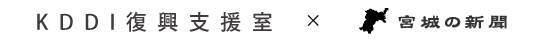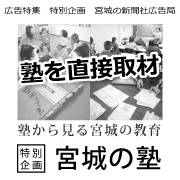取材・写真・文/大草芳江
取材・写真・文/大草芳江
2009年03月12日公開
2009年03月30日追記
科学だけをするのが科学者、じゃなくてもいい
瀬名 秀明 Hideaki SENA(作家・東北大学工学部機械系特任教授)
1968年生まれ、静岡県出身。薬学博士。1990年東北大学薬学部卒。1996年同大学院薬学研究科博士課程修了。1995年に『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を、1998年に『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞を受賞。1997年4月~2000年3月、宮城大学看護学部講師。2006年1月、東北大学機械系特任教授に就任。小説の他にも、文芸誌や科学誌で科学と人間に関したコラムや対談を多くこなしている。
「科学って、そもそもなんだろう?」を探るべく、【科学】に関する様々な人々をインタビュー
その人となりをそのまま伝えることで、「科学とは、そもそも何か」をまるごとお伝えします
東北大学大学院薬学研究科の博士課程在学中に、
140万部を売上げたベストセラー『パラサイト・イヴ』で、作家デビューした瀬名秀明さん。
文芸界、薬学部、大学病院、看護学部、工学部...これまで様々なコミュニティーで、その価値観の
違いを、「違和感」として感じ続けてきた瀬名さんだからこそ見える、これからの科学者・作家像とは。
瀬名さんは、違和感を感じる能力を「我々の脳が持つ、非常に人間らしい能力」とし、
その感覚を意識し顕在化させることが、「今後のサイエンスやアートの重要な本質になる」と見る。

作家の瀬名秀明さんに聞く
―科学って、そもそもなんだろう?というテーマで、様々な立場の方から、お話を伺っています。
瀬名さんは、東北大学大学院薬学研究科博士課程に在学中、『パラサイト・イヴ』で作家デビュー。
薬学博士で(薬剤師の免許も取得)、宮城大学看護学部の常勤講師も経験され、
今年度までは、東北大学工学部の特任教授(機械系)を務めてらっしゃいます。
このように様々な立場を経験した方が、科学をどのようにとらえているのか。
本日はそこを中心に、お話を伺えればと思います。
科学者にもなりたかったし、小説家にもなりたかった
―研究が生活の中心となる博士課程在学中(しかも薬学)で「小説を書こう」と思う方、
さらに作家デビューまでされる方は、非常に珍しいのではないかと思います。
うちは父親も母親も、薬学部出身なんですよ。
父親は研究者でして、母親は薬学部で同級生の父と結婚したのです。
父の鈴木康夫は、中部大学生命健康科学部の教授をやっています。
昔の静岡薬科大学、今の静岡県立大学で、薬学部教授をやっていました。
僕は子どもの頃から、父の研究室へ遊びに行っていました。
ですから薬学というか、生物系の研究室が、身近にあったんですね。
母親は、ミステリーがすごく好きで、
アガサ・クリスティや仁木悦子、夏樹静子の小説をよく読んでいました。
ですから、小説や映画、テレビ、そういうものを見るのが、わりと近かったのですね。
その両方がもともとあったので、
科学者にもなりたかったし、小説家にもなりたかったんです。
小説は趣味で、小学生の頃から書いていました。
大学生になったら、研究者をやりたいということで、研究の方をやりました。
実験が非常に楽しくて、毎日学校に行っていましたが、
大学院生くらいになると、いろいろなことやりたくなりますよね、人間って(笑)。
ちょうど、たまたま日本ホラー小説大賞が創設されたので、
そこに応募してみようということで、夏休みを使って小説を書いたわけです。
本当は、夏休みはないし、研究しないといけないのだけど、
あえて夏休みをとって、休んで(笑)。
そして2年目で、『パラサイト・イヴ』でデビューした、と。
―研究も小説も、やりたいものをそのままやり続けた、ということですか?
そうですね。
ただ、ひとつちがうのは、『パラサイト・イヴ』を書く前までは、
科学を題材にした小説を書いたことはなかったんです。
それまでは、普通のサスペンスやミステリーでしたので、
科学小説を書くとはじめて意識したのは、『パラサイト・イヴ』からですね。
なぜならば、1回目(日本ホラー小説大賞)の応募作で、
普通の純ミステリーを書いたのですが、四次予選までいって落ちたのです。
それが、大学院博士課程1年の頃です。
編集者の方からは「また来年も応募してくれ」という手紙が来ましたので、
是非、応募したいと思いました。
では、前回よりも更に上へ行くには、どうすれば良いのか。
あまり他の人が知らない業界を書いた方が、珍しがってもらえるのではないか。
そう考えて、はじめてサイエンスの分野を書こうと思ったんですね。
―それまで、科学を題材にして小説が書かれることは、一般的ではなかったのですか?
ないことはなかったと思うんですよ。
例えばアメリカでも、マイクル・クライトンがアンドロメダ病原体をはじめとして、
科学を題材にしたベストセラー小説を出していましたし、あったとは思うんです。
けれどもその多くは、SFというジャンルで書かれていて、
一般的な方が読むものとして認識されていなかった、というのがひとつですね。
もうひとつは、マイクル・クライトンのように、お医者さんが小説家になるケースは、
日本ではわりと多いのですよ。例えば、森鴎外や渡辺淳一先生がそうですね。
つまり、お医者さんが人間をよく見て、人間の本質をとらえて、
そこに医学的な見地を絡めながら作品を書いていくことは、
昔から日本の伝統としてありました。
けれども自然科学の分野、細胞やDNAなどをやっていた人が小説を書くのは、
日本であまりなかったんですね、実は。だから、珍しかったのだろうと思います。
そのふたつだと思いますね。
自分の専門分野を書いただけでは、『パラサイト・イヴ』はできなかった
―はじめて科学を題材にして小説を書くことで、新たに気づいたことはありますか?
最初は単純に、『パラサイト・イヴ』は細胞の怪物が襲ってくる話に
しようと思っていたんですよ。
けれどもそのとき、NHKスペシャル「生命 40億年はるかな旅」という番組がありまして。
生命の40億年近い歴史を、非常に綺麗なCGで、月一回ずつ放送していたんです。
その第一目の特集が、まさにミトコンドリアの話だったんですよ。
昔、酸素があまりない時代に、生命が誕生したわけですが、
やがて毒である酸素を取り込んで、エネルギーにできる細胞が登場した。
そのふたつの細胞が、共に生きる共生をできるようになって、
わたしたちの直接の祖先である真核細胞ができたのだ、ということをやっていたわけです。
そこで、「あぁ、ミトコンドリア、俺が実験でやっているよ」と(笑)。
当時の僕は、ミトコンドリアの脂肪酸代謝に関する研究を行っていました。
僕らがものを食べると、最終的にはミトコンドリアの中で消化されて
エネルギーになるわけですが、そのときにミトコンドリアの働きがうまくいかないと、
血液中に脂肪などが貯まって、高脂血症や動脈硬化などの病気を引き起こしてしまいます。
そのようなことを防ぐために、ミトコンドリアをうまく機能するような薬があるわけですが、
その薬に関する研究を、僕はしていたのです。
あぁそうか、ミトコンドリアは、医学的な研究対象でもあるけれども、
進化を象徴するものでもあるし、わたしたちの生命とは何かということに、
密接に関係しているのだということが、改めてそこでわかるのですね。
ですから、研究対象というものは、
ひとつのところから見ると、ひとつの面しか見えないのですけれど、
ミトコンドリアといったときには、いろいろな側面があるわけです。
それを進化人類学的に見る人もいれば、
健康や代謝の観点で見る人もいるし、がんで見る人もいる。
いろいろな方法があるわけですね。
研究というのはつまり、自然界にあるものは、
様々な研究のアスペクトを重ね合わせないと駄目なんだなと思いました。
そういうことを二十何歳で、なんとなく感じたわけです、その番組を見ながら。
そういう面が出せると、良いホラー小説になるんじゃないか。
そこにはじめて気づいて、『パラサイト・イヴ』のプロットができた、というわけです。
『パラサイト・イヴ』は、自分の専門分野を書いた、とよく言われる小説ですが、
自分の専門分野を書いただけでは、あのようなストーリーにはならないですね。
自分とは全然違うタイプの研究というのもあるんだとわかって、ようやく書けたというかね。
そういう小説ですね。
―専門細分化された専門の研究をしていると、その専門とは違う側面から研究を位置づけることを
忘れがちになる傾向が一般的にありますが、
瀬名さんは小説を書くことで、別のいろいろな側面を見たのですね。
書くことによって、そういうこともわかりましたね。
一流の科学者は、自分の研究対象をいろいろな側面から見られる能力があると思います。
例えば、『パラサイト・イヴ』を書いた後で、映画をつくることになり、
そこではじめて、日本医科大学大学院・加齢医学研究科の
太田成男先生と一緒に仕事をするようになるわけです。
昔から太田先生の論文は読んではいましたが、
その太田先生が、映画の監修もやられていたので、
はじめてちゃんとお話しするようになって。
そこで今度、一緒にミトコンドリアの本を書きましょう、ということになって、
『ミトコンドリアと生きる』と『ミトコンドリアのちから』という二冊の本を書くわけです。
この本は、太田先生が下書きをして、
僕がリライト(rewrite)して全体像をまとめる形で書いたのですが、
太田先生とかなり、全体の章立てから構成を、二人で話し合うわけですよ。
すると太田先生はミトコンドリアというキーワードから、
本当にいろいろなものを引き出してくるわけですね。
例えば、先程お話した生命の起源ですね、それから生命の進化、
人間の健康、人間の老化、そして死。
つまりミトコンドリアは、生病老死のすべてに関わっていますし、
なぜわたしたちが生きて育って老いて病気になって死ぬのか。
実はこれは全部、もともとミトコンドリアがわたしたちの体に入って、
エネルギーをつくる工場になったからだ、と。
その工場はすごく性能の良い工場なのだけど、
性能が良いがゆえに欠点もある。
なぜかというと、非常に大きなエネルギーを生み出すので、
そこにどうしてもですね、有害な物質をつくってしまわざるを得ない。
そういう宿命を負っているわけですね。
だからこそ、わたしたちはその宿命によって、
病気になってしまったり、老いたりするわけです。
そして我々は生殖をするわけですが、
生殖で受精卵細胞をつくりあげていくのにも、ミトコンドリアが関係している。
次世代をつくるのにも、ミトコンドリアが関係しているのです。
ということで、生命の進化の歴史を辿ると、
わたしたちが、なぜ健康であったり、なぜ病気であるのかもわかるのだ、と。
わたしたちの健康というものに、生命36億年の歴史が入っているのだ、
ということを、本の中に構成するのですね。
一流の研究者は、そういう視点ができるのです。
太田先生もおそらく僕の本を読んでくださって、
そういう視点というものが、若いなりに多分入っていると思ってくださったから、
一緒に本を書きましょう、とおっしゃってくださったんだと思うのですね。
そういうことを、小説家になることによって、僕自身は気がついてですね、
その後も、ノンフィクションや小説の中で、
そういうことを書き続けていくことができた、ということなのです。
サイエンスやアートの力
―そんな瀬名さんから見る、サイエンスとは?
僕はね、「まなざし」という言葉を良く使うんです。
「まなざしの力」は、私が大好きな漫画家・坂口尚さんが、よく漫画の中で書いていた話で、
どうやってその現象を見るか、どうやって今の世界を見るか。
その力が、世界を変えていくし、自分を変えていく、ということなのです。
僕らは、ともすると、毎日毎日ですね、この現在の瞬間しか考えないんですよね。
今、特に不況の時代ですし、「10年後のことを考えましょう」と言っても、
そんなことを考えるより、明日の飯の方が大切だとか。
わりとそういうことが現実的だと、考え込んじゃうんですね。
つまり、未来とか将来とか過去とかを忘れて、
とにかく今を、なんとなく生きなきゃいけない。
そのような意味では、非常に本能的になるわけです。
それは生命が、毎日毎日を生きるのに非常に重要な能力なのですが、
一方では人間というのは、未来を考えたり、過去のことを思い返したり、
自分の今の衣食住とは、直接関係ないことも考えられるのです。
その直接関係ないことを考えたときに、直接的には関係ないのだけど、
実は、間接的にはすごく関係しているんだ、とかね。
なぜかというと、わたしたちは非常に複雑な社会の中に生きていて、
単に、食っちゃ寝、食っちゃ寝だけではないですよね。
そういう中で、何か今までぼんやりと暮らしていたときに、
自分はこういう風にして生きているんだ、相手はこういう風にして生きているんだ、
わたしたちはこういう風にして生きているんだ、
そういうものに気づくツールとして、やっぱり科学、人文社会や自然科学があるのだろうと。
そのひとつに、さらにアートや小説というものもあるのではないかと。
人間らしく生きるという点での、「まなざしの力」を鍛錬する、とでも言いますか。
自分とは直接関係ないように思えることも考えることが、
ひいては人類全体のためになるし、自分のためにもなる、さらに自分の子どものためになる。
そういうことが、人間に与えられた脳の力だと思うのですね。
そういう脳の力を助けたり、さらにもっと発展させたりするのが、
自然科学を含めたサイエンスや、アートの力だと思っています。
―そのように見れば、サイエンスもアートも並列なのですね。
科学の研究をするのも、アートをするのも、
その成果を見て驚いたり感動したりするのも、人間、おもしろいんです。
科学者は、自然界の中にある真実なり真理なりを見つけていきますよね。
今までよく見えなかったものを、ぱっと見られるようにするわけです。
その見方というものを、発見していくわけですよね。
工学者は、今までうまくできなかったものを、
アイディアや工夫で形にしていくわけです。
人文社会の人も、そうだと思うのですね。
なぜこんな社会なんだろう?と思ったときに、過去のことを勉強することで、
今の時代の位置づけが、わかったりするでしょう。
今まで見えにくかったものを、見せてくれる。
その中で気づきがあったり、おもしろみがあるわけです。
アートも、やはりそういうもので、
今までもやもやしていたものを、斬新な視点で、ぱっと見せてくれたりするわけですよね。
良いアート、おもしろいアートは、社会を変えるわけです。
例えばSFでも「サイバーパンク」という画期的な小説が、1980年代くらいに出たわけです。
全てが良い小説だったとは思いませんけど、
人間とロボットが融合したり、人間とバーチャルの世界の境界がわからなくなったり。
すると皆、これはすごい世界観だということで、それを実現しようというエンジニアが現れ、
いつの間にか、なんとなく我々は、電脳社会にもう生きているわけですよね。
社会が変わるわけです。
それは、技術によってもそうですね。
インターネットという技術をつくることで、社会が変わるわけです。
ですから、サイエンスにしろ、テクノロジーにしろ、小説・アートにしろ、
人をおもしろがらせて、社会を変える力がある。
そのおもしろさは、両方とも同じだと思いますね。
やり方はいろいろあるにせよ、社会の新しいアスペクトを切り開くわけです。
小説だけを書くのが小説家、でなくても良い
―瀬名さんはこれまで、いろいろな立場から、科学のさまざまな側面を見られてきたと思います。
ここまでのお話は、瀬名さんの中で、ずっと変わらないスタンスと解釈してもよろしいですか?
先程そうは言いましたが、僕はわりと、一般論、理想論を言っていたと思うのです。
そうは言ってもね、やっぱり金融危機で不況ではないか、と。
どんどんリストラもされていて、失業しているではないか、と。
もう世界では戦争も起こっていて、ぼろぼろじゃないか、と。
そんな、科学がおもしろいとか言ったってね、全然役に立たないでしょう。
そう言う人も、わりといると思うのですけどね。
僕はデビューして14年になりますが、
この14年間で変わったと言えるし、変わっていないとも言えると思う。
やっぱり14年前の僕が大学院生だった頃は、
学生が小説を書いて、小説家としてデビューして、
小説家をやりながら研究もやるということは、ほとんど考えられなかったし、
教授の先生方から見れば、感覚的にも許されなかったことだと思うのですよね。
『パラサイト・イヴ』も薬学部が舞台ですけど、だからと言って、
薬学部の先生方が喜んだかというと、必ずしもそうではなかったと思うのですよ、当時。
「そんなことをやっている暇があるなら、研究しなさい」という人も多かったと思います。
それから今度は、仮にも研究者の卵の人がミトコンドリアが怪物になって襲ってくるなんて、
非科学的な小説を書いて、皆を怖がらせてお金を儲けている、とか。
そういうことは、科学者倫理にも劣るんではないか、とか。
そういう学生を輩出する東北大学の教育はなっていない、とか。
真面目にそういう批判がマスメディアに出たんですね、当時。
つまり、自分たちのコミュニティーというものがあって、
その中に、異質なものが入るのを恐れるわけです、みんな。
研究者なら研究者として人生を全うするのが当たり前だし、
皆の協調を乱してはいけないし、そこで仕事をすれば良いじゃないか、と。
作家の世界も、そうだと思うんですよ。
だから、このように大学で特任教授をやるというのは、
作家として視点がぶれてるとか、やりたいことが定まっていないとか、一途ではないとか、
そういうことを、わりと言われてきたと思うのですよ、昔はね。
今は、でも、少しずつ変わってきたと思います。
作家というものも、トータルで表現する。
その中には、研究や教育活動があっても良いのではないか。
全部が変わってきているとは思わないけど、一部は変わってきている。
東北大学だって、少しずつ変わってきていますよね。
僕のスタンスという最初のご質問に戻ると、
僕は小説も好きでしたし、科学も好きだったわけですね。
多分ね、教育も僕、そんなに嫌いじゃないと思うんだよね。
本当は、小説家でやるんだったら、小説だけやればいいし、
研究者だったら、研究だけやればいいし、
教育者だったら、教育だけやればいいのですけど。
けれども、それだけではおもしろくないのです、自分の中では。
だから、いろいろなことをやる、と。
まだね、例えば文芸業界の人は小説が主たるフィールドだろうと思います。
僕はいろいろノンフィクションを書いているのですが、
文芸業界の人は、僕のノンフィクションを小説家の余技だと思っていることでしょう。
科学業界の人は、私の小説をちゃんと読んでいるかというと、読んではいないでしょうし、
僕が文芸業界の人を連れてきたら、彼らはすごく居心地が悪くなるでしょう。
学生さんは学生さんで、僕の作家の素顔は、多分知らないでしょう。
ですから僕が付き合っているそれぞれの人はまだ、それぞれのコミュニティーなのですよ。
けれども僕は、わりと全部が、自分の全体の表現と、なんとなく思っているんですね。
それが今後のサイエンティストでもあるし、作家でもあるのだろう。
という希望を、というか、期待をしているわけです、自分の中で。
将来は、こういう風になれば良いな、という期待ですよ。
だから、やっている。
研究者自体も、それが研究者の本来の姿と思わない人も、当然たくさんいるでしょう。
けれども今、例えばね、これから研究者や作家を目指す人は、
別に小説だけを書くのが小説家でなくても良いのだよ、
研究だけするのが研究者でなくても良いのだよ、という風には言ってあげたいですね。
もちろん才能も努力も必要だと思いますし、僕自身才能があるとは思いませんが、
やろうと思えばできる、と。
その土壌は、この10年くらいで少しずつできてきたよ。
君達は、もっと昔よりは、もっと充分に才能を発揮できるよ。
そういう風に言ってあげたい。
そういうスタンスですね。
―既存の枠にとらわれず、より多様な人が、それぞれの力を発揮できるような土壌が、
この10年で少しずつ、整ってきているということですか?
適材適所だと思うのですよね、最終的には。
研究だけにものすごい能力を発揮する人って、いると思うのですよ。
例えば、こうやって記者の方に喋るのがすごく苦手で、
本を書くのもすごい苦手、テレビに出るのもすごい苦手。
けれども研究は素晴らしい、という人もいます。
一方では、話すのはすごくうまい。
けれども研究はたいしたことない、っていう人だっているんです。
そして、両方できる人もいるんですよ。
両方できる人はこれまで、どちらか一方しかやらせてもらえなかったり、
両方やろうとすると、社会が「そんなことはいかんよ」という風に抑えたりしたんです。
けれども、いろんなことができる人が、あるいは、いろいろなことをやりたいという人が、
やってもいいですよ、そういう能力あるんだったら伸ばしなさい、
と社会が言ってくれるようになってきた、ということですね。
―瀬名さん自身、ひとつの枠だけに、納まる方ではなかった。
自分の経歴で、どうしてもそういう風に考えるようになってしまったのです。
最初は薬学部でした。そして薬学の大学院に一度落ちて、一年間技官をやって、
また大学院に戻るわけですけど、今度は薬学の研究棟ではなくて、
医学の病院、大学病院の薬剤部というところで研究をさせて頂きました。
そこで、実際の薬剤師さんやお医者さんと共同研究をするようになるのです。
つまり、研究だけをやっていれば良い社会ではなくて、そこには実際に患者さんがおり、
生きている人がおり、全然違うコミュニティーの薬剤師さんやお医者さんがおり、
考え方も違う、やり方も違う、科学に対する考え方も違うわけです。
そこで、小説家としてデビューすると、また文芸の世界の考え方も全然ちがう。
次に、宮城大学の看護学部へ行きました。
看護学部の先生方の考え方も、全然違う。
彼女達の考える、科学のあり方も全然違う。
学生さん達はそういう中に入って、
学問と、実際に患者さんを診る看護の間のギャップに、非常に悩むわけです。
そのように考えると、ひとつの世界だけで、
ずっとその研究をできたわけではなかった。
自分が専門家として訓練を受けてきた、そのベースとなる科学観と、
今自分がいるコミュニティーのもつ科学観との、葛藤というのが常にあったんですね。
あぁ、自分はこういう風に科学のことを考えていたけど、
この人たちは違う科学観を持っているのだ、と。
じゃあ、むこうの科学観と自分の科学観、
一体何をすり合わせて、どんな新しいことをできるだろうか。
そういうことを、考えなければいけない。
一方では、サイエンティフィックよりも、もっと下のレベルで、
今日のこの会議はどうやってまとめましょうとか、
あの先生はすごく嫌なやつなのだけど、どういう風につきあいましょう、とかね。
そういう面が、非常に大きいんですよね。
だからつまり、先ほども言ったような感覚を、
自分の中でも、希望として持っているわけです。
違和感を、クリエイティビティにつなげる
―瀬名さんのお話からは、まさに社会そのものの中を生きてきた、という気概を感じます。
個人的な話になりますが、社会では立場によって考え方が想像以上に異なることを感じますし、
一見同じような立場でやっているように見えても、実は、全然違う価値観やスタンスだったりします。
それこそ、今わたしのいるビジネスの世界と科学の世界は、考え方や価値観が全く違いますし、
特に理学的な価値観は、ビジネスの世界では認識されない場合も多いです。
けれどもその中で、どの世界でも伝わる価値あるものをつくらなければ、と日々感じています。
そういうものを、小説の中で表現していったり、
あるいはサイエンスとして表現できたら、新しいものができるのではないかと思うわけです。
最近『瀬名秀明ロボット学論集』という本を出したのですよ。
あそこで、わりと、そういう考え方を書いているんです。
僕、数年前からですね、<境界知>という言葉を言いはじめていて、
これは、こういう<境界知>というものが、わたしたちの人間らしさをつくっている、と。
さっきのね、違和感というものを感じる能力ですよ。
そういう違和感をうまくクリエイティビティやイマジネーションにつなげることができれば、
わたしたちの生活や未来は、もっともっと、おもしろいものになっていくのではないかと。
そういう境界知をうまく発揮するような、あるいは、
うまくサポートするような科学技術のあり方っていうのも、ありだよね、
という話を、実は書いているのです。
例えばさっき、コミュニティーが違うというお話をされましたし、その通りなのですけど、
なんでわたしたち、コミュニティーが違うって、感じるのでしょうね。
それは非常に不思議ですよね。
それはわれわれの脳が持っている、非常に人間らしい能力だと思うのですよ。
昔はね、違和感というものは、ない方が良いのだ、という風に思われていたと思うのです。
例えば、海外へ留学に行きました。
期待に胸膨らせて行きましたが、むこうでは、食習慣も生活習慣も宗教観も、全然違う。
同じ研究をしているはずなのに、同僚と、なかなかうまくいかない。
でもなんとか、アメリカのやり方で、文化に馴染んでいこう。
けれども、どうしても日本人という壁があって...という風に悩んだりすると思うのですね。
このように「壁はない方が良いのだ」と思われてきたと思うのです。
バーチャルリアルティーの研究も、壁をなくす方向へ、どんどん進歩してきたと思います。
例えば、むこうに遠隔操縦のロボットアームがあって、こちらで操縦している。
むこうとこちらで、微妙に動作が違ったりすると、まずいですよね。うまく操縦できない。
この違和感をうまくなくしていくのが、バーチャルリアルティーの技術だったわけです。
つまり、違和感を、つるつるにしていく技術だったわけです。
けれども我々、どんなことがあっても、つるつるにはならないですね。
逆に言えば、つるつるにならない違和感とは何かをちゃんと見極めて、
それを何か新しいプラスの方向に転換できないだろうか。
だって我々、例えばアメリカに行ってうまくいかないと思った時に、工夫しますよね。
例えば、もっと話し合いましょうとか、こっちはこうしましょうとか。
工夫するってこと、それはクリエイティビティですよ。
もしもつるつるだったら、あるいは、「もう相手が僕とは全然違う文化だから、
どうでもいい、相手が良いようにやらせましょう、こっちはこっちでやるから」
と言って断絶してしまえば、何も工夫は要らないですよね。
けれども、断絶もしないし、つるつるにもならない工夫をしていく。
それが実は、今後のアートやサイエンスのすごく重要な本質になるのではないかと、
僕自身はなんとなく感じるのです。
それがロボット学の中にあったり、看護学の中にあったりするのではないかと思うのです。
だって、ロボットと人間は、必ずそのどこかでコミュニケートしないといけないですね。
ロボットというのは動くので、動くもの同士が、やはりどこかでつながらないといけない。
だから、つるつるのロボットというのはありえないので、
必ずどこかでロボットと人間の境界というものが生じるわけです。
そこを如何に豊かな共生関係にするか、それは非常に重要な問題です。
看護学でも、患者さんひとりひとりによって、全然違う部分があるわけです。
その一方で、身体というものは良くできていて、
こう動かせばこう動くとか、そういう部分もある。
ベースラインとして、こういう風にすれば、基本は大丈夫だっていう部分はある。
でもその一方で、一人ひとりによって、何が快適で何が不快かは、全然違う。
だから、それぞれの人に合った、きめ細やかな看護をするためには、
どこに違和感があって、どこに違和感がないのかということに、
すごく敏感になりながら、看護していかなければならない。
それは今までの医学とか物理学とは、ちょっと違うタイプのサイエンスだと思うのですね。
そういうサイエンスは20世紀にはあまりなかったので、
21世紀にきっと広がっていくのではないかと思うのです。
―これまで様々なコミュニティーの間で、違和感を感じてきた瀬名さんだからこそ見える、
これからのサイエンスやアートの本質、そしてそれが瀬名さんならではの表現となるのですね。
そうやって多様な立場の人たちが、それぞれ感じる違和感を突き詰め、
それをかたちにすることで、これからの未来は一歩一歩、つくられていくのだと感じました。
◎
未来について考える
―東北大工学部機械系の特任教授としては、どのようなことをされているのですか?
僕は、2006年1月に、東北大工学部機械系の特任教授に就任したんですね。
そもそものきっかけは僕の取材で、当時神戸大助教授だった田所諭先生と知り合い、
何度か話をしていくうちに、「今度、東北大教授になることが決まって東北へ行くので、
ぜひ瀬名さんも何か一緒にやりましょう」という話になったんです。
そこで、その当時の機械系の清野慧先生(2007年3月退官)が尽力してくださって、
僕を特任教授にしてくださいました。
そこでのミッションは、
やはり手塚治虫の漫画を読んでね、工学を目指した研究者の人がたくさんいる。
だから100年後の未来の子ども達や若者に何か影響を与えるような、
そういうことが、作家と研究者の両方で、共同しながらできると素晴らしい。
そういうことができるプロとして、機械系に特任教授を呼びました、と。
そう言ってくださって、僕はそれに非常に感激しました。
「じゃあ、やりましょう。では具体的に何をやりましょう?」
「授業はやった方が良いですか?」と聞くと、
「授業はやっても・やらなくてもいいです」と言われたので、
「じゃあ、やりません」と。
「会議もたくさんあるんですよね?会議も出たほうが良いですか?」と聞くと、
「会議は出ても・出なくてもいいです」と言われたので、
「じゃあ、出ません」と(笑)。
「じゃあ、何をやればいいですか?」と聞いたら、
「瀬名さんは、その代わり、小説を書きなさい」と。
「瀬名さんが大学の中で、教授、若手、学生さん、
色々な研究者の人たちと話をすることで、瀬名さんが良い小説を書いて、
それが100年後の人たちに良い影響を与えてくれるなら、それでいいのだ」と、
当時、清野先生はおっしゃってくださったのです。
それに僕は感激したわけです。
でもね、いろいろあるので(笑)、
隔週で「瀬名秀明が行く」というコーナーをウェブサイトでやって、
先生方や学生とのディスカッションを発信しました。
それから、大学がやっている広報活動も、いろいろとお手伝いしました。
それと、東北大の先生ではないのですけど、
知り合いの先生で僕とほぼ同年代くらいの脳科学や複雑系の友達がいるので、
その人たちと一緒に研究もやっていまして。
それについては、『ロボットのおへそ』という本にも載っていますが、
今後、ロボットと人間が一緒に暮らす社会ができます。
そういうときに、いろいろなシチュエーションがあるわけですけど、
そういうものをシミュレーションできるような、プラットフォームがなかなかないね、と。
ならば、ロボット研究者だけではなくて、
例えば、動物行動学を研究をしている人とか、脳の研究をしている人たちも含めて、
いろいろなシミュレーションができるプラットフォームをつくりましょう。
そういうものを、僕のもともとのアイディアのひとつも入って、実際につくっています。
そういう研究も、実際にやっていると。
それから、大学院生の学生さん達との自主ゼミもやっています。
「未来について考えるゼミ」というもの。
それは機械系だけではなくて、他の大学院生の方々も参加しています。
例えば、皆で楽天の試合を見たり、小川洋子さんの「博士の愛した数式」を読んだり、
皆でガンダムの映画を見たりして、それをもとに、
それと自分の研究もちょっと絡めながら、未来はどうなるかとか、皆で語り合う。
例えば、小川さんが数式の美しさのようなものを文学で表現しているのなら、
自分の研究と照らし合わせて、そういうものに対してどう思うか、とか。
機械系だけではない、いろんな学生さんが来ることで、
違うコミュニティーの意見を聞けますから、非常にお互いに刺激になる。
未来ということを、普段はあまり考えないけれども、
ゼミのときくらいは、ちょっと考えてみよう、そういう鍛錬をしましょう、
そういうゼミもやっています。
そういうことを、3年間やってきたということですね。
―これまでの瀬名さんの考え方・生き方を、まさに体現する取組みですね。
言葉よりも、呼吸で語りたい
―瀬名さんは作家ということで、最後に、表現についても聞かせてください。
小説のテーマについては、一貫したものはあるのですか?
作家には、いくつかのタイプがあると思います。
毎回毎回、テーマも書いていることも全然ちがう人も、当然いると思うのですよ。
一方では、わりと似たようなテーマというか、
一貫したテーマをずっと追いかけている人もいると思いますね。
僕はどちらかと言うと、後者の方で、
やっぱり「生命とは何か」とか、「人間の知能」とか「心とは何か」とか。
わりとそういうテーマに、なっていくんですよね。何をやろうとしても。
多分、飛行機の小説を書いても、そういう風になるんですね(笑)。
だから、それは自分の何か、興味の核があるのでしょう。
そういうのも全然関係なくやる人もいますよ。
それは、資質だと思います。
―瀬名さんは、26歳で『パラサイト・イヴ』を書いて、27歳でデビュー。
わたしの歳(26歳)とほぼ同じということを考えますと、とても親近感が湧きます。
もうねえ、昔のことだね。
若い頃のことなんて、そろそろ、だんだん忘れてきているからねぇ(笑)。
僕の好きな作家で、アイラ・レヴィンという人がいたんですよね。
その人、23歳でデビューしたのですよ。
それで、23歳になったとき、流石にあせりましてね。
アイラ・レヴィンは23歳でデビューしているのに、俺は一体何をやっているのだろうと。
あと僕の同年齢で、一回も会ったことはないのですけど、佐藤賢一さんという人がいてね。
東北大学文学部の出身で、『ジャガーになった男』で小説すばる新人賞を受賞して、
今は直木賞作家(1999年『王妃の離婚』で第121回直木賞受賞)ですけど、
この人がデビューしたのが、25~26歳の時なのです。
これは、やれた、と。
俺も、うかうかしてられないと思いましたね(笑)。
―普段から相当ひとつひとつの物事を認識して、更に「これをかたちにしたい」というものがないと、
あれ程の緻密さで構造化していくことはできないなぁと。同じ26歳と思うと、なおさらそう思います。
でも、26歳くらいだったら、できるんじゃないの?
あの時ならではの集中力で、できたのではないでしょうか。
今はまた、当時とは違う集中でやっています。
―どのような集中ですか?
ぬるい集中で(笑)。
集中しているとは思いますけど、当時とは違うと思いますよ。
『パラサイト・イヴ』って、あれね、5ヶ月で書いている小説なんです。
しかも最初の3ヶ月は、週末しか使っていないんですよ。
ですから、実質3ヶ月くらいで書いているんです、あの小説。
800枚くらいの小説を。
今800枚の小説を3ヶ月で書けと言われても、僕、多分無理ですよ。
すごい集中力だったと思います、当時。
一日15枚とか20枚とか、平気で書けましたもん。
アパートの横の空き地で盆踊りをやっていようが、原稿を書いていましたからね。
そういう意味では偉いですわ、当時。
―逆に、歳を重ねるにつれ、リアルに感じるものが変わっていくのでは?
そうですね。
だから昔書けなかった小説が書けるようになったと思う、確かに。
―今だからこそ書ける小説とは?
あのですね、人間は変わっていく、っていう小説です。
当時は、出てくる登場人物は、キャラもバシッと決まっていて、
この人はこういう風に考える人、こう行動する人、と決めて書いていたと思うのですね。
けれども今は、ストーリーの中で、人間性は変わる。
最初はこうだった人が、こういう風になる、とかね。
だんだん流されていくなり、自分の意志なりして、
変わるという小説は少しずつ、書けるようになったと思うのですね。
あとは、あまりくどくどは説明しなくなった。最近。
―それは、シンプルになっていくということですか?
シンプルというよりかはね、
なんだろうねぇ
・・・
言葉よりも、なんかね、呼吸みたいなもので語りたくなるんだよね。
僕が息を吸って吐いている、そういう感じで伝えたい。
僕ね、昔の『パラサイト・イヴ』とか読むと、
今とは全然文体が違うのですけど、すごく機能的なんですね。
ここは「こういうことを感じてもらいたい」とか「こういうことを考えてもらいたい」とか、
「こういうことを説明したい」とか、そういうために、すごく機能している文章なんです。
今の僕が読むと。それはそれで、わかりやすいのね。
その機能はすごく良くできていると、今だに自分でも思うのだけど、
だけど、それ以外の機能が、そこにないんだよね。
だから、どっちが良いという問題じゃなくて、
今はその機能以外のなんかちょっと別のね、呼吸のようなもので、
全体を表現してみたいなぁという方向に、今、自分の中で振れている段階です。
またちょっと変わるかもしれません、その辺は。
―呼吸ということは、あまり他人を意識しないで書く、ということなのですか?
機能するっていうことは、確かに相手のことを考えているのですね。
ただその機能することの中に、個性があまりないんだよね。
他の人も、機能できるでしょう。
そうじゃない表現をするということが、
むしろ、相手のものなしにも、つながるのではないか、と。
言い方が難しいなぁ。
例えば、映画があるじゃないですか。
いろいろな俳優さん、女優さんが出てきます。
例えば、誰でも良いのですけど、レオナルド・ディカプリオが主役をやっていたとします。
他の俳優でも、それができたかもしれない。
例えばマット・デイモンでもできたかもしれない。
だけどディカプリオだからこその雰囲気が出るって、あるじゃない。
そうやって、監督さんって、俳優を選ぶわけですよね。
どういう俳優さんを当てはめるかとか、例えば同じプロットなのだけど、
サンフランシスコじゃなくて、ニューヨークのほうが舞台にふさわしいとか。
そういうものに、ちょっと近いんじゃないかな。
ですから、マット・デイモンではなくて、
ディカプリオの息で機能をする、ということじゃないかな。
文章自体に、なにか身体性があるのですよ。
そういうのが、理想だな、最近は。
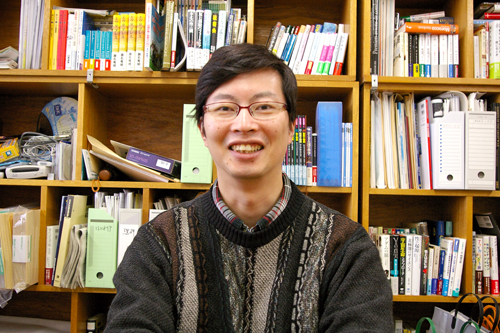
【追記】(2009.03.30)
サイエンスを作品の構造として表現する
―最後に、瀬名さんにとって、そもそも表現とは何ですか?
テーマとして、どのようなことを書きたいか。
それを表現するとき、例えば脳をテーマにするときは、小説を脳の構造にしたり、
ミトコンドリアをテーマにするときは、小説をミトコンドリアの構造にします。
『パラサイト・イヴ』は、ミトコンドリアをテーマにした小説。
ミトコンドリアは、生命のエンジンのようなものであるし、
エンジンのようなものであるからこそ、排気ガスのように悪い物質を出してしまう。
エンジンを発火させるがために、老化や病気になってしまうし、死というものがある。
生病老死や進化と密接に関わっています。
論文ひとつだと、専門ひとつに特化してしまいますが、
全体を書くことは、小説ならできるので、
生命のエネルギーを感じさせるようなつくりにしたかったし、
進化や病気にも直結しているようなものにしたかった。
『BRAIN VALLEY』は、脳をテーマにした小説です。
小説の舞台は、脳を模した「ブレインテック」という研究所。
脳は非常に複雑で、いろいろと不思議なことをやっている。
小説全体も、脳の複雑さを表現したかった。
つまり、テーマと表現というのは、密接に関連しているのです。
「こう表現したい」と思ったら「こういうストーリー」と、
自分の直感として決まってきます。
科学を小説にするということは、そういうことなのだろうと思うのです。
僕は、基本にはエンターテインメント作家、読者を楽しませる作家です。
エンターテイメントには、読者に気持ちよく楽しく読んでもらうための
フォーマット、定式がしっかり決まっています。
そこから外れてしまうと、芸術性は高くなるけど売れなくなる。
僕はその定式は嫌いではないですが、外れたところでも可能性を見出したい。
では、どこで折り合いをつけるのか。
それが作家のオリジナリティとなるのでしょう。
僕は、エンターテインメントを基盤にしながらも、
僕が考えるサイエンスを表現できないだろうか、ということを考えています。
どうやったら表現できるかはわからないけれども、
ミトコンドリアなら本質はこういうものだろう、そういうものを、
作品の構造として表現するのが、僕のアプローチだろうと思うのです。
僕はエンターテインメント作家ですが、他の作家と僕とで違うところがあるとすれば、
扱うテーマによって、常に表現を新しくつくってみたいという欲求があります。
そのような意味で、長編小説では、同じテーマは扱っていません。
それぞれで表現を超えたい。
しかしながら全体で見ると、「生命とは何か」「人間とは何か」、
根底に流れている大きなテーマはあるようです。
例えて言うならば、飛行機で空を飛んでいると、むこうに水平線や地平線が見えます。
あの辺まで見えたな、というのがあるな、ひとつの作品を書いて。
ところが見えてしまうと、むこうの先の雰囲気が感じられる、なんとなく。
次はあの辺でやろうかな、というものが。
そして、後ろを振り返ってみると、なるほど、
そういうことをやっていたのだな、というものがある感じです。
科学を書いている作家は他にもいます。
例えばマイケル・クライトンは、マイクル・クライトンの書き方で書いている。
同じように書けば、受けることはわかっていますが、
彼とは違う書き方を、書きたいのです。
同じ人間ではないのだから。
表現を広げたい、
表現に可能性を見つけたい、という気持ちがあります。
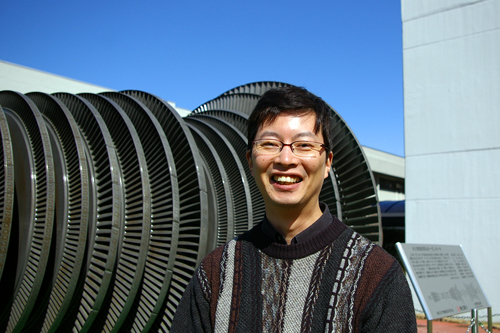
―瀬名さん、本日はどうもありがとうございました。
コラボレーション
おすすめ記事
 |
【特集】宮城の研究施設 一般公開特集 |
 |
【特集】仙台市総合計画審議会 仙台の10年をつくる |
【科学】科学って、そもそもなんだろう?

若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 【大草 芳江|科学って、そもそもなんだろう?】

地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】

青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 【大草 芳江|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?|防災科学技術研究所】

前田拓人さん(弘前大学)に聞く:<東日本大震災から10年>もし東北地方太平洋沖地震が起きていなければ、地震研究はどうなっていた? 2021.10.08 【大草 芳江|弘前大学|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?】
同じ取材先の記事
◆ 東北大学

地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】

日野亮太さん(東北大学)に聞く:<東日本大震災から10年>もし東北地方太平洋沖地震が起きていなければ、地震研究はどうなっていた? 2021.10.02 【大草 芳江|東北大学|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?】

【レポート】東北大学未来科学技術共同研究センター創立20周年記念講演会/中鉢良治さん(産総研理事長)招待講演「豊かな社会とは?-科学技術の視点から-」 2020.06.05 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】
科学って、そもそもなんだろう?
最新5件
 |
若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 |
 |
地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く) 2023.01.26 |
 |
地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 |
 |
「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~ 2022.03.02 |
 |
青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 |
■記事一覧を表示 記事カテゴリ > 科学って、そもそもなんだろう? | |
カテゴリ
取材先一覧
■ 幼・小・中学校
■ 高校
- ・仙台一高 (15)
- ・仙台二華 (14)
- ・仙台二高 (12)
- ・仙台城南高校 (5)
- ・仙台城南高等学校 (0)
- ・仙台高専 (4)
- ・宮城一高 (4)
- ・宮城県高等学校理科研究会 (2)
- ・岩ケ崎高 (1)
- ・東北工業大学高校 (0)
■ 大学
■ 国・独立行政法人
- ・内閣府 (1)
- ・宇宙航空研究開発機構 (5)
- ・文部科学省 (0)
- ・東北経済産業局 (17)
- ・水産総合研究センター東北区水産研究所 (1)
- ・理化学研究所 (3)
- ・産業技術総合研究所東北センター (36)
- ・科学技術振興機構 (1)
- ・防災科学技術研究所 (1)
- ・高エネルギー加速器研究機構 (1)
■ 自治体
- ・仙台市 (8)
- ・仙台市博物館 (4)
- ・仙台市天文台 (12)
- ・仙台市教育委員会 (13)
- ・仙台市産業振興事業団 (1)
- ・仙台市科学館 (8)
- ・仙台文学館 (2)
- ・仙台管区気象台 (2)
- ・塩釜市 (3)
- ・宮城県 (8)
- ・宮城県古川農業試験場 (2)
- ・宮城県教育委員会 (1)
- ・宮城県農業・園芸総合研究所 (1)
- ・気仙沼市 (1)
- ・登米市 (1)
■ 一般企業・団体
- ・DIC株式会社 (2)
- ・K sound design (1)
- ・KDDI (2)
- ・natural science (1)
- ・せんだい・みやぎNPOセンター (2)
- ・てとてと (1)
- ・ひのき進学教室 (11)
- ・みやぎ工業会 (8)
- ・みやぎ工業会会長 (0)
- ・みやぎ産業振興機構 (3)
- ・アスター (1)
- ・インスペック (1)
- ・エツキ (1)
- ・ソニー (3)
- ・ソニー教育財団 (1)
- ・ソフトバンク (1)
- ・ティ・ディ・シー (1)
- ・デュナミス (1)
- ・ドットジェイピー (1)
- ・ナノテム (1)
- ・ハリウコミュニケーションズ (3)
- ・ハード工業有限会社 (1)
- ・フジイコーポレーション (1)
- ・プレファクト株式会社 (1)
- ・ヤマダフーズ (1)
- ・全国学習塾協会 (3)
- ・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (1)
- ・勝山酒造部 (1)
- ・及源鋳造株式会社 (1)
- ・大武・ルート工業 (1)
- ・太白少年少女発明クラブ (1)
- ・宮城の新聞 (0)
- ・宮城県中小企業家同友会 (1)
- ・宮城県産業人クラブ (0)
- ・宮城県職業能力開発協会 (1)
- ・宮城県酒造組合 (2)
- ・工藤電機 (2)
- ・平孝酒造 (1)
- ・応用物理学会 (2)
- ・新東総業株式会社 (1)
- ・日刊工業新聞社 (7)
- ・日本アンドロイドの会 (1)
- ・日本技術士会 (2)
- ・日本私立大学団体連合会 (1)
- ・日本農芸化学会東北支部 (1)
- ・日本IBM (3)
- ・日東イシダ (1)
- ・有限会社 柏崎青果 (1)
- ・東京エレクトロン宮城 (1)
- ・東北ニュービジネス協議会 (1)
- ・東北活性化研究センター (3)
- ・東北経済連合会 (1)
- ・東北電力 (2)
- ・東北電子産業株式会社 (1)
- ・東栄科学産業 (1)
- ・林精器製造 (1)
- ・株式会社三栄機械 (1)
- ・株式会社悠心 (1)
- ・河北新報 (1)
- ・神田産業株式会社 (1)
- ・秋田化学工業 (1)
- ・笹氣出版印刷 (1)
- ・米鶴酒造 (1)
- ・萩野酒造 (1)
- ・農芸化学会 (1)
- ・遠藤工業 (1)
- ・鈴木製作所 (1)
- ・阿部蒲鉾 (1)
- ・阿部蒲鉾店 (1)
- ・鳴子の米プロジェクト (1)
- ・NECトーキン (1)
特別企画 「宮城の塾」
 |
学習塾から見る 宮城の教育の「今」 塾選びに一役 |
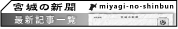
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く) 2023.01.26 |
 |
【社会って、そもそもなんだろう?】 【同窓生に聞く#01】中鉢良治さん(元ソニー社長、産総研最高顧問)がリアルに感じていることって、何ですか? 2022.10.27 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 |
 |
【社会って、そもそもなんだろう?】 「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~ 2022.03.02 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 |
記者ブログ

|
ひとり新聞社「宮城の新聞」の大草よしえが衆院選に立候補 2021.10.19 |

|
最近の活動は「Twitter」に移行しました 2019.11.01 |

|
【追記】テレビ朝日「モーニングバード」スタジオ生出演&iCAN'15世界大会(アラスカ)世界第1位! 2015.06.19 |

|
2014年の振り返りと、2015年の抱負 2015.01.05 |

|
平成25年度を振り返りました・・・。 2014.04.02 |
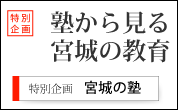
 |
中野塾(泉中央・北高森) |
 |
ひのき進学教室(泉中央・長命ヶ丘・八幡教室・上杉教室) |
 |
夢学館(東照宮・福室) |
 |
早稲田育英ゼミナール(泉中央) |
 |
ソーメック個別学習院(若林区、太白区、泉区に6教室) |
 |
明和塾(北山・八木山) |
 |
JUKU ペガサス仙台南光台教室(南光台南) |
アクセスランキング
- 【宮城の塾】 宮城の塾 仙台市を中心とした学習塾・幼児教室・進学塾の特集
- 世界中の研究者が憧れる研究拠点へ/東北大学WPI-AIMR本館竣工記念式典/科学って、そもそもなんだろう?
- [vol.1] 第1回宮城の日本酒を楽しむ会/社会って、そもそもなんだろう?
- 「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~/社会って、そもそもなんだろう?
- 宮城県仙台第一高等学校/教育って、そもそもなんだろう?
- 【宮城の塾】 ひのき進学教室(泉中央本部教室・八幡町教室・上杉教室・五橋教室・長町教室・愛子教室・吉成教室・大和町教室、他)
- 地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く)/科学って、そもそもなんだろう?
- 【宮城の塾】 JUKU ペガサス仙台南光台教室
- 【宮城の塾】 質問できます!/宮城の塾|宮城の新聞
- 【宮城の塾】 明和塾(北山教室・八木山教室)