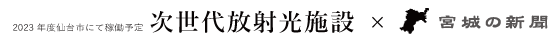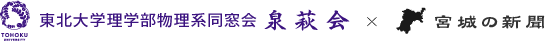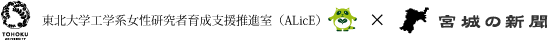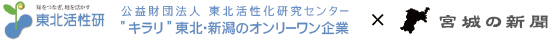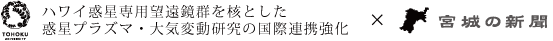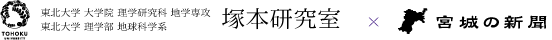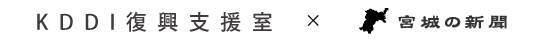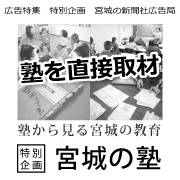取材・写真・文/大草芳江
取材・写真・文/大草芳江
2009年02月02日公開
2009年6月10日加筆修正
言葉になるもの・ならないもの その両側面が科学の本質
野家 啓一さん(東北大学大学院文学研究科・文学部教授)
1949年仙台生まれ。宮城県仙台第一高等学校卒業、東北大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院科学史・科学基礎論博士課程中退。南山大学専任講師、プリンストン大学客員研究員などを経て現在、東北大学文学部教授。専攻は科学哲学、言語哲学。近代科学の成立と展開のプロセスを、科学方法論の変遷や理論転換の構造などに焦点を合わせて研究している。また、フッサールの現象学とウィトゲンシュタインの後期哲学との方法的対話を試みている。主な著書に、『言語行為の現象学』『無根拠からの出発』(以上、勁草書房)、『物語の哲学』(岩波現代文庫)、『科学の解釈学』(ちくま学芸文庫)、『パラダイムとは何か』(講談社学術文庫)など、多数。1994年第20回山崎賞受賞。
「科学って、そもそもなんだろう?」を探るべく、【科学】に関する様々な人々をインタビュー
科学者の人となりをそのまま伝えることで、「科学とは、そもそも何か」をまるごとお伝えします
「科学って、そもそも何だと思いますか?」
哲学者の野家啓一さんは、「それは難しい質問ですね」と微笑み、こう話しはじめた。
「大体、日本語の科学という「言葉」は、訳のわからない「言葉」ですよね。
科学の"科"って、一体何でしょう?」
ものの見方・考え方と、「言葉」の働きには密接な関わりあいがある。
時空を超えて「言葉」を追いかけることで、「科学とはそもそも何か」に迫る。
それと同時に野家さんは、「言葉」になる部分だけでなく「言葉」にならない部分の
両側面を押さえていなければ、科学の本質はわからないだろう、と警鐘を鳴らす。
科学の発展に必要な細分化は、「木を見て森を見ず」という問題を生んだ。
森を見て感じる人間の身体感覚を、科学者も市民も取り戻さなければ、
科学と社会を結びつける回路はできてこないだろう。森を見る哲学者は、そう話す。

哲学者の野家啓一さんに聞く
―「科学」とは、そもそも何なのでしょうか?
それは難しい質問ですね(笑)。
大体、日本語の【科学】という言葉は、訳のわからない言葉ですよね。
数学なら数の学、物理学なら物の理の学、生物学なら生物の学、社会学なら社会の学です。
ところが【科学】というのは、「科」についての学問ですね。
では、「科」とは一体何でしょうか?
学「科」や百「科」事典、「科」目の科ですね。
つまり【科学】とは、いろんな「科」目が寄せ集まって体系化された学問、
という意味なのです。
―【科学】には、それだけの意味しかないのですか?
私たちが【科学】に抱くイメージとは随分と異なる気がしますが、一体なぜなのでしょう?
もともと【science】という言葉は、ラテン語の【scientia(スキエンティア)】を語源として、
英語に14世紀頃入ってきたと考えられています。
【scientia】は、英語で言えばknowledgeです。
つまり最初は【science】も、単なる知識という意味で使われていました。
knowledgeは、数えられない名詞(不可算名詞)ですね。
(knowledgeをknowledgesと複数形で書くと英語のテストで×になります)
ですから【science】も、はじめ英語に入ってきた時は、
「知識」という意味でしたから不可算名詞でした。
【sciences】という複数形はなかったのです。
しかし16世紀から17世紀にかけて、科学革命という出来事が起こりました。
1543年にコペルニクスが『天球回転論』という本を書き、地動説を発表するわけです。
1687年にはニュートンが『プリンキピア』、
その原題は「Philosophiae naturalis principia mathematica(自然哲学の数学的諸原理)」
という本を書いて、現代の物理の基礎を築きます。
16世紀半ばから17世紀の終わり頃にかけヨーロッパを中心に起こった、
この知識の地殻変動と呼んでも良いような出来事が、「科学革命」と呼ばれているわけです。
―単なる知識という意味の【science】に、どのような革命が起こったのでしょうか?
このときはじめて、科学の方法、methodが確立されました。
ひとつは、論証です。
論証と言えば、ギリシア時代まで遡りますが、
ユークリッド幾何学やアリストテレスの論理学の論証など、
ものごとを理詰めで文章に表し、文章間の前提と帰結の関係性、すなわち推論関係を調べていくのが、論証です。
もうひとつは、実験です。
実験とは、実際にやってみて、経験によって確かめるということです。
ですからexpriment(実験)とexperience(経験)は語源を同じくします。
これが発達したのは、アラビア地域、イスラム圏です。
ギリシア科学は紀元前に発達したのに対して、
アラビア科学が発達したのは、だいたい9世紀から10世紀のことです。
この時期ヨーロッパは中世でしたが、キリスト教の影響が強くて、
今のような科学的な考え方は芽生えませんでした。
そしてヨーロッパでは主に12世紀頃から、アラビアから実験科学を輸入することになります。
例えば、ギリシアのプラトン、アリストテレス、ユークリッドの著作はいったんアラビア語に訳され、
12世紀にヨーロッパへと逆輸入されたのです。それを「12世紀ルネサンス」と呼んでいます。
そこではじめて、ギリシア起源の「論証」の方法と、
アラビア起源の「実験」の方法が結びついて、
西洋の近代科学の基盤が築かれたと考えて良いと思います。
―科学はヨーロッパで生まれたと思い込んでいましたが、実は半分がアラビア起源なのですね。
例えば、chemistry(ケミストリー:化学)という言葉は、
もともとはアラビア語のalchemy(アルケミー)という言葉から来ています。
最初の「al」はアラビア語の冠詞で、英語の「the」にあたります。
そう考えてみると化学用語には、「al」がつく単語が非常に多いことがわかります。
alcohol(アルコール)、alkali(アルカリ)、aldehyde(アルデヒド)...
それから数学のalgebra(アルジェブラ:代数)、コンピュータのalgorithm(アルゴリズム)もそうです。
このように化学や数学の用語には、アラビア起源のものが多いですね。
他にも時計の1時間が60分なのは60進法を採用しているからですが、
これもアラビア起源ですし、ご存知のように時計の文字盤はアラビア数字で記されています。
このように近代科学がアラビアに負っているものは、実は非常に大きいのです。
ですから近代科学とは、ヨーロッパで生まれたものではなく、
ギリシアの論証精神と、アラビアの実験精神が結合して生まれたものです。
科学の半分は、アラビア・イスラム起源なのです。
つまり、ちょうど日本が明治維新の頃、
アメリカやヨーロッパから科学や技術を輸入したことと同様の状況が、
12から13世紀のヨーロッパでも起こっていたということです。
そこで科学的なものの見方・考え方の基盤が形づくられて、
それが一斉に熟成し花開いたのが、コペルニクスからニュートンに至る150年間、
「科学革命」の時期と言えると思います。
【science】は知識からはじまった、と先ほどお話しましたが、
それが科学革命を経ることによって、論証と実験という科学的方法に基づいて
経験的に実証された法則的な知識という意味を、【science】は持つようになります。
つまり知識の中でも、科学的方法、経験的な手続きによって実証された知識、
という特別な意味をもつことになるのです。それが今日の【科学】の出発点ということになります。
―私たちが抱く【科学】のイメージに、だんだんと近づいてきた気がします。
けれどもまだ、【科学】の「科」の謎が解けていませんね。
ニュートンの『プリンキピア』の原題は、先ほどもお話したとおり
「Philosophiae naturalis principia mathematica(自然哲学の数学的諸原理)」です。
ここでいう自然哲学とは、今日でいう物理学に相当します。
コペルニクスやケプラー、ガリレイ、ニュートンは、
当時、【scientist(科学者)】ではありませんでした。
【scientist】は、19世紀の半ばにできた言葉です。
では、ガリレオやニュートンは、自分を何と思っていたかと言えば、
哲学者だと思っていたの。自然哲学者です。
その自然哲学が、次第にその後、色々な分野に分かれていきます。
物理学とか化学とか、地質学とか、生物学とか。
つまりそれは、専門分化していくということです。
専門分化が著しく進んだのが、19世紀の半ばです。
自然哲学が専門分化して、いろんな自然科学の分野に分かれていった。
それを総合して、【sciences】と複数形で呼んだ。
この時はじめて、【science】という言葉は、可算名詞になったのです。
正確には、日本における「科学」という言葉は、不可算名詞の【science】の訳語ではなく、
複数形の【sciences】の訳語なのです。
専門分野の総称として、まとめて【sciences】と呼んだわけです。
科学というのは百「科」とか分「科」の学、
つまり色々な分野に分かれた学問というのが、【科学】の語源です。
そういう意味では、「科学」という言葉はつまらないですね。
単に色々な分野に分かれた学問、という話なだけであって。
宇宙の真理を探究するとか、経験的に実証された体系的知識とか、そういう意味では全くないのです。
―なぜ当時の日本人は、【science】ではなく【sciences】に着目して訳語をつくったのでしょうか?
明治時代は必ずしも【science】の訳語として、
【科学】という言葉が定着していたわけではありませんでした。
「究理学」や「格物学」など、儒教用語を借りて色々と訳されましたが、
最終的に残ったのが、【科学】と【理学】でした。
理学は今も、理学部に残っていますね。
理というのは理(ことわり)・法則ですから、理学の方が【science】の訳語としては適切なのではないかと思います。
けれども19世紀の半ばに学問の専門分化が起こり、
【scientist(科学者)】という言葉ができました。
「科学者」という言葉ができたのは、1840年前後のことです。
それはどういうことを意味するかと言うと、
科学を職業として営む人たちが出てきたということです。
それまでの科学の担い手は、遺伝学のメンデルは修道院長ですし、
近代の化学革命を成し遂げたラヴォアジエは税務署の役人ですし、
今年で生誕150年となるダーウィンは大金持ちの坊ちゃんでした。
食うには困らなかった貴族や僧侶や大金持ち、修道院や税務署など定職についている人たちが、
その余暇に趣味として科学を研究していたのです。
つまり、アマチュアだったのですね。
「amateur(アマチュア)」という言葉は、「love(愛)」を意味するラテン語 amorに由来します。
アマチュアとは、ひとつのことを愛する人、という意味です。
別の職業を持ちながら、ある分野を愛てアマチュアとして研究するのが、その頃の科学者でした。
科学を研究して食っていこうというプロを目指す人はいなかった。科学では食えなかったんです。
けれども19世紀になると次第に、理工系の学校ができますし、
企業でも科学的知識を必要とする研究開発が行われるようになって、
次第に科学で飯が食えるようになってきました。
そのときはじめて、【scientist(科学者)】という言葉ができてきたわけです。
それと共に、学問が個別科学化、専門分化してきて、それぞれに学会ができます。
天文学会とか、医学会とか、地理学会とか。それによって、学問の骨組みと知識の再生産システムができます。
そういう風に、科学が社会システムとして成立したのが、19世紀の半ばで、
それを「第二次科学革命」と言います。
すなわち、17世紀の「第一次科学革命」では、
論証と実験が結びついて、科学の方法が確立されました。
それに次いで19世紀半ばの「第二次科学革命」では、
教育機関ができたり、学会ができたりして、科学が社会システムの中に組み込まれました。
ちょうど19世紀の半ば、日本では何が起こっていたかといえば、幕末から明治維新ですね。
その頃に岩倉使節団は、ヨーロッパ各国をまわって、科学や技術のあり方を吸収してきたわけです。
ヨーロッパはちょうど、第二次科学革命の終わった頃、
あるいは最後段階を迎えていた頃です。
社会システムとしての科学、教育組織や学会組織がヨーロッパで完成されたときに、
運よく日本は科学を輸入したり、視察へ行ったりしたのです。
ちょうどそれは、【science】が【sciences】になった時代に当たります。
ある一定の方法に基づいて獲得された知識という意味の【science】が、
専門分野に分かれた【sciences】という学問体系になった時期です。
ある意味では、理学を【science】の訳語とし、科学を【sciences】の訳語と考えれば、
ちょうど【science】から【sciences】への転換というものを、
【理学】から【科学】への呼称の変化が象徴していると言えるかもしれません。
現在の日本では、「科学技術」という言い方をします。
我々は「科学技術」をひとつの言葉として考えるでしょう。
けれどもヨーロッパでは、科学と技術は別ものだという考え方があるので、
科学技術のように一語であらわすことはできないのです。
あくまで「science & technology」と言います。
―私はいつも「科学・技術」とするか「科学技術」とするかで迷います。
ヨーロッパが、科学と技術を別物と考える理由はどこからくるのでしょう?
ヨーロッパでは、科学はあくまで学問的知識、技術は職人技です。
ギリシア時代やローマ時代、当時の技術はてこ・輪軸・滑車ですが、
職人技というのは、奴隷がやる仕事でした。
機械を扱って物を動かすような仕事は、奴隷階層の仕事だということで軽蔑されてきたのです。
「liberal arts(リベラル・アーツ)」は自由学芸と訳されます。
教養と言ったら良いでしょうか。昔はどの大学にも教養部がありましたね。
英語名は、「college of liberal arts(カレッジ・オブ・リベラル・アーツ)」です。
中世の大学ではリベラル・アーツが基礎科目として教えられましたが、
主に数学に関わる4科目の算術・幾何・天文・音楽の「四科」、
主に言語にかかわる3科目の文法・修辞学・論理学の「三学」、あわせて7科目があります。
リベラル・アーツは、「liberal citizen(自由市民)」が学ぶべき教養だとされました。
自由市民というのは、奴隷ではない人、という意味です。
ですから市民が学ぶべきは学問的知識であって、技術的な技能ではありませんでした。
それが自由市民が学ぶべき教養科目なのであって、
てこ・輪軸・滑車などの機械を扱うメカニカル・アーツ(機械技術)は奴隷階層、職人階層の仕事と考えられていたわけです。
―日本人には階級の差がないから、科学と技術の区別がないのですね。
第一次科学革命の時期は、シェイクスピア(1564-1616)が活躍した時代と重なります。
シェイクスピアは戯曲「ヘンリー四世・第2部」の中で「mechanical and dirty hand」という言葉を使っています。
シェイクスピアを日本ではじめて翻訳した坪内逍遥(1859-1935)は、
この言葉に「けちな、下等なやつら」と訳語をつけました。
mechanicalは、決まったことしかできない、
昔奴隷がやっていた仕事をやるという、dirty と並ぶ軽蔑的な形容詞でした。
「実はシェイクスピアではないか」と疑われた哲学者にフランシス・ベーコン(1561-1626)がいますけれど、
彼の著書『ニュー・アトランティス』や『学問の進歩』を見てみると、
mechanicalという言葉が「規則正しい」とか、ポジティブな意味で使われています。
つまりこの頃に、機械技術に対する考え方は、次第と変化してきたと考えられます。
18世紀に刊行された『百科全書』では、「リベラル・アーツ」に対する「メカニカル・アーツ」の優位がはっきりと主張されています。
しかしながら、大学はなかなか保守的な組織なので、
技術教育・エンジニアリングを、今でいう工学部のような形で取り入れることはしませんでした。
中世ヨーロッパの大学には、神学部・法学部・医学部の3つの上級学部と、
その下に下級学部として哲学部がありました。
哲学部は、今でいう理学部と文学部をあわせたもので、学芸学部とも言われますが、先述のリベラル・アーツを教えていました。
大学はこの4学部制をとっていたわけですが、その中には技術教育は入っていなかったのです。
近代になって、ナポレオン(1769-1821)がヨーロッパを席巻するようになると、
軍事技術の開発のために、科学的知識や技術開発が必要になってきました。
そのためにナポレオンは大学とは別の組織として、
「Ecole Polytechnique(エコール・ポリテクニック)」という理工科専門学校をつくりました。
ドイツでは、「Technische Hochschule(TH)」という高等工業専門学校がつくられました。
大学とは別に、技術教育、エンジニアリングの研究開発をする教育機関をつくったわけです。
古い制度を守り続けてきた大学には入れなかったんですね。
そのために大学の外に高等教育機関を設けて、ヨーロッパ各国の政府は技術者育成をしたのです。
ところが先程あなたが鋭く指摘したとおり、
日本には技術や職人仕事を軽蔑する意識や伝統はありませんし、
むしろ職人技と尊敬される風土がありますよね。
世界ではじめて大学の中に工学部をつくったのは、どこだと思いますか?
―技術に対して抵抗感がないのは日本、ならば東京大学ですか。
その通りです。
フランスやドイツでは大学の外につくったのに対して、
日本では何の抵抗もなしに、テクノロジーの部門を大学の中に組み込みました。
今から見れば大変先駆的なこととも言えます。
日本人には、科学と技術の区別はなかったのですね。
ですから日本がヨーロッパから学問を輸入するときも、
両者を区別をしたわけではなくて、一緒にして輸入しました。
日本にとっては当時の富国強兵や殖産興業に役立ったと言えますが、
ヨーロッパからすると、日本は基礎をぶんどって行って、
応用だけに力を注いでいるという批判はあります。
けれども学問に対する考え方が、そもそも日本とヨーロッパとでは違っているのです。
純粋科学というものに対する考え方が異なっているのでしょう。
日本には科学の基礎になっている「自然哲学」に相当する学問がありませんでした。
例えば日本が中国から輸入した算術は、和算として独自の発達を遂げ、関孝和によって
ニュートンの微積分とほぼ同じレベルにまで達しました。
けれども和算は、パブリックな学問ではなく、茶道や華道に類する一種の芸事です。
ですから公開で討論して真理を探究してという形ではなく、
お茶などと同じように一子相伝で、自分の子供だけに、秘伝として伝えられました。
ヨーロッパのような公共的な知識の観念は、日本では薄かったのです。
技術においても、江戸時代のからくり人形など、精巧にできていましたが、
知識を共有して新しいものを共同でつくろうというより、
子々孫々まで秘伝として伝えていこうという形でした。
そもそも科学の一番根本にある自然哲学的な考え方は、日本には生まれませんでした。
学問においては、日本は儒学が中心ですね。
人を治める政治学や身を修める倫理学、道徳哲学が発達しました。
つまり修身・斉家・治国・平天下、そういった方面が日本の学問の中心にあったので、
ヨーロッパのように宇宙を支配する法則を探求する自然科学のような学問の発展はなかったのです。
唯一日本であったのは、蘭学ですね。
日本はオランダを通じて、医学や天文学などの蘭学を輸入しました。
ただオランダ医学でも、中国から輸入した漢方医学でも、
どういう薬がどのような症状に効くかということは日本で詳しく研究されましたが、
どうしてそうなるかのメカニズムまで探究しようという態度はあまりなかったようです。
―【science】ではなく【sciences】の訳語としての【科学】が残ったのは、
科学が社会システムとして組み込まれ、専門分野に分かれていった時代に学問を輸入したことに加え、
そもそもの学問に対する日本とヨーロッパの考え方・捉え方の違いがあるのですね。
◎
―野家さんは東北大学理学部物理学科をご卒業後、哲学に転向されていますが、
野家さんが科学哲学を選んだ理由を教えてください。
今から振り返れば、何らかの意味では、昔から科学や哲学への関心を持っていたのだと思います。
科学に興味を持ったのは、ジョージ・ガモフ(1904-1968)の
『1,2,3...無限大』という本を中学のときに友達から借りて読んだのが、きっかけでした。
相対性理論や量子力学などの話題が、青少年向けに解りやすく解説されており、
科学に対する興味をかきたてられました。
物理学を学べば、宇宙の謎がすべて解けるのではないか。
ガモフ全集10巻を読んでそう思い、物理をやろうと目標を定め、
東北大学理学部物理学科へ入りました。
ガモフ全集は現代科学の最先端の動きを伝えてくれると同時に、
今思えば、哲学的なものの見方、私が惹かれたのはそういうところでした。
物理学を学べば、時間とは何か、空間とは何か、宇宙の果てはあるのかなどが、
わかるのではないかと思い物理学科に入りましたが、実際の物理は実験などの現場仕事が中心で、
自分がイメージしていた物理学と現場の物理学の間にギャップを感じました。
さらに1960年代から1970年代は大学紛争の真っ只中。
そして公害が社会問題化していた時代でしたので、
科学と社会の関わり方、科学のあり方を考えざるを得なくなりました。
そういうところから次第に、物理学そのものよりも、
物理学的な考えのしくみや、社会に与える影響、つまりは科学史や科学哲学という方向へ
関心が次第にシフトしていったのです。
―野家さんのアプローチ方法とは、どのようなものですか?
ひとつは、「分析哲学」とも言われますが、言葉や論理を手がかりにすることです。
論理学(logic)の語源はギリシャ語で「logos(ロゴス)」と言い、
これは宇宙を支配している法則をも意味します。
「はじめに言葉(ロゴス)ありき」と新約聖書「ヨハネ伝」の冒頭の文章にもありますが、
ロゴスは言葉や論理であると共に宇宙の秩序でもあり、手で掴めるものではありません。
けれども概念や観念というものは言葉を通じて操作されるもので、
概念を組み換えて新しい思考形態をつくりだしていくのですから、
ものの見方・考え方と、言葉の働きには密接な関わりあいがあります。
大森荘蔵さん(野家さんが東京大学大学院時代に師事)の影響もあって、
言葉を分析することを通じて、概念、事物あり方、ものの見方・考え方、理論のしくみを
追求していく方向へと進んでいきました。
―先程も、言葉を分析することで「科学とはそもそも何か」に迫っていましたね。
けれどもそもそも、ものの見方・考え方は、すべて言葉となるものなのでしょうか?
核となる言葉による理解ですが、もちろん言葉にはならない直感的把握も重要な役割を果たしています。
そういうところは、言葉だけでなく、身体で認識しています。
物理化学者であると同時に科学哲学者だったマイケル・ポランニー(1891-1976)は、
それを「暗黙知」と呼んでいます。
暗黙知とは、ポランニーによれば「我々は言葉にできることよりも多くのことを知ることができる」というこことです。
例えば、自転車に乗れるけれども、その乗り方を言葉で説明することはできません。
反対に言葉で説明されても、自転車に乗れるわけではありません。水泳なども同じですが、体で覚える部分はあるわけです。
哲学者のギルバート・ライル(1900-1976)も、
それをknowing thatとknowing howと区別して呼んでいます。
言葉で説明してもわからない。
けれども実際にやってみたりすることで理解できるし、可能になること。
そういう側面のことです。
ですから、私はこれまで言葉になる部分を追求してきましたが、
科学の中にも、実験操作を通じて、体で覚えていくとわかる部分があるのは確実なことです。
その両側面を押さえていなければ、科学の本質はわからないでしょう。
もうひとつは、最近、遺伝子組み換え食品の安全性やBSE問題などがありましたが、
科学者が理論的に説明する「安全」という概念と、市民が「安心」して食べられるという概念の間には、
ギャップがありますね。
科学者が説明して「安全」だというのと、
それでも「口に入れるものなので何となく嫌だな」という市民の感覚。
科学的合理性からは「安全」だとわかっていても、
社会的な合理性から見ると「安心」できないというところがあって、
そういう意味では、科学と社会の間に、ある種のギャップがあります。
そのことも、単なる頭だけの知識として科学を理解するのではなくて、
身体感覚として「おかしい、嫌だ」と感じるものがあった上で、
科学的な合理性とすり合わせていくことが、
科学の側にも、社会の側にも求められていくのだろうと思います。
―もともと科学的な合理性とは、ある前提のもとに言えることだと思うのですが、
細分化された今の社会ではその前提を感じづらく、科学を相対化する機会が少ないと感じています。
科学というのは、ある前提のもとで行われている知的作業です。
実験室のミリグラム単位の物質が市場に出て、社会の中で流通しだすと何トンも蓄積されるわけです。
けれども科学者が頭の中で考えるのは、ミリグラム単位。
その物質が何トンも社会に放出されたとき、どうなるかについては余り考えもしない。
昔は、実験室でつくられたものが、市場にすぐに出まわることはありませんでした。
実験室で発見された成果が実用化され、
何ステップかを経て市場に出回ることになるまでは、それなりの時間がかかったのです。
その間に、社会的な影響に対する議論を行う時間も充分に持てたわけです。
しかしながら科学技術の発展によって、実験室でできたものが、
市場に出されるサイクルが今は極端に短くなっています。
食卓と実験室が地続きになってしまいました。
これからは、どうすれば安全と安心をつなぐ回路、
つまり科学と社会の間に「実験室と社会をつなぐ回路」を見つけられるかが重要な課題になってきています。
そのときに、最後に頼りになるのは、市民の身体感覚、つまり暗黙知が重要になるでしょう。
普通、昆虫や蛇を食えといわれれば、躊躇しますよね。
身体感覚は、もちろん飢えれば食いますので絶対的なものではありませんが。
虫酒や蛇酒は美味しいらしいですけどね(笑)。
今はその身体感覚を超えて、技術的な進歩が早いから、
さまざまなアレルギーや新型インフルエンザなど身体が対応できなくなっている。
そのような状況だからこそ、逆に身体感覚を大切にしなければならないと思います。
身体感覚も脳科学で解明できるのかもしれないけど、
脳科学で解明できたからって、蛇が好きになるわけではないですからね。
―科学と人間の身体感覚との乖離が社会に与える影響とは、どのようなものでしょうか?
先程も言いましたが、科学は、論証と実験の二つの要素で成り立っています。
論証は頭の中で操作できるけど、
実験は実際にやってみて、具体的なものから抵抗を受けながらやるわけですね。
そのときには、こうすればこうなると思っても、うまくいかないことがあります。
近代科学の中核にある構成的実験とは、余計な要素は切り捨てて、理想的な条件のもとで必要な要素だけを取り出して操作することです。
自然はそのままではとても複雑ですから、単純に要素だけ取り出すことはできませんが、
科学はできるだけ単純な要素に分解して、人間の認識にとって必要なものを取り出しています。
一方、身体は自然が持っている複雑さを同時に持っています。
自然を相手にするにしても、科学はできるだけ対象を単純化しようとしていますが、
自然は変化し続けているので、複雑さを片方に置いておかないと、
自然を単純化しすぎて、人間の都合にひきつけすぎてしまうのではないでしょうか。
例えば医学で言うと、病気は治ったけれども患者は死んだということになりかねない。
また、生態系の破壊や環境汚染などが生じてしまう。
自然の複雑さをもういっぺん、身体で感じ取りつつ、その条件を単純化することが大切です。
そのあたりが、実験室での操作は、余計な要素を取り除いて、自然を純粋化することですが、
純粋化された自然が本当の自然だと思い込む錯覚があるように思います。
実際の自然は、色々な条件が絡まりあっています。
レイチェル・カーソン(1907年-1964)が『沈黙の春』で告発したDDTは、
非常に有効な農薬でした。
DDTは、害虫を取り除くという意味では有益な農薬です。
けれども害虫というのは、人間にとって、勝手に害だとか益だとか言っているもので、昆虫にはあずかり知らぬことです。
では害虫を殺せばいいのかと言えば、それで生態系のサイクルが狂ってしまうわけです。
木を見て森を見ない。
細分化は学問の発達にとって必要なことですが、科学が細分化されるにしたがって、
私たちは自然を全体として相手にしていることを忘れがちです。
すると良いと思ってしたことが、結果として最悪な事態を起こすことになりかねません。
実験室において、法則なり新物質なりを取り出すために、
対象を細分化して、機器に閉じ込めて、条件を純粋化するにしたがって、
全体の自然を切り取って操作していることを忘れがちになるということですね。
環境問題、食糧問題、温暖化問題、エネルギー問題など、
人間が、これまで細分化的な方法でやってきたところが、全体のバランスが崩れ、コントロールできないことになっています。
これらの問題は技術的に解決できると考える人がいるけれども、
私はそれは楽観的過ぎると思っています。
もちろん、対症療法的な方法として技術的な進歩もあるでしょうが、
それがまた別の副作用を起こすことがあり得ます。
自然の全体像を人間はある意味、忘れてきました。
細分化して分析する方向のみ進んできたので、全体のバランス感覚を失いかけています。
しかし、新たなものごとに出会ったときに、嫌だなと不愉快に感じる身体センサーが
人間にはもともと備わっています。
賞味期限間近になっている食べ物も、匂いを嗅いでみて、
腐っているようだったら食べないでしょう。
元々人間にはセンサーが備わっているので、賞味期限などの文字に惑わされるよりは、
身体感覚を信じたほうが良い。
ですから害になる食べ物かそうでないかは、文字に書いてある何月何月が重要なのではなくて、
自分で匂いを嗅いだり味をみり、身体感覚で確かめた方が、はるかに確実だと思います。
お腹を少々壊しても、別に死ぬわけではないでしょうから。
―本来備わっているはずのセンサーも、使わなければ全体像を感じられなくなるでしょうか?
使わなければセンサーは摩滅していくのではないでしょうか。
歩かなければ足の筋肉が弱るのと同じです。
人間は、正確にものごとを把握しようと、あらゆることを数値化してきました。
しかしながら数値に頼って、もともと持っていた人間の感覚が、
その能力を使わなかったために、退化していると思いますけどね。
学生時代、私はワンダーフォーゲル部でした。
山に登ると、頭で考えたことは役に立ちません。
もちろん考えはするけど、現場に立ってみないとわからないことがある。
やはり本で読んだことでわかるのではなくて、実際に体験することでわかってくるし、
感覚を研ぎ澄ますことができます。山に登って天候の変化や岩場の危険を感じる、そういう感覚です。
最近はカーナビもありますから、方向を確かめる必要がなくなりました。
すると、方向感覚も退化していきます。昔は、北極星を頼りに旅をしてきたわけですからね。
技術的には発展して、人間は余計な能力を使う必要がなくなったけど、
身体感覚は退化して、生きる力、サバイバル能力を下げているのではないかと思います。
―哲学という立場は、科学を一歩ひいたところから捉えることができるのですね。
科学と社会の関係性というように。
一歩退いた立場で見ないと、その中にどっぷり漬かったのでは、見えるものも見えなくなると思いますね。
―では現場の科学者が、社会とのつながりをもつことは、難しいことなのでしょうか?
最先端の現場から、一歩ひくことは難しいことだと思います。
けれども思想家の吉本隆明(1924-:作家のよしもとばななの父)が次のようなことを言ってました。
外界を知らないという意味の「井の中の蛙」という表現がありますが、
「井の中の蛙」だって、自分が井戸の中の蛙であることを認識すれば、
井戸の外に出ることをしないでも、外部の世界とつながることができる。
ですからその言葉を借りるとするならば、科学と社会のあり方を考えるときに、
科学の外に出る必要はなくて、科学は社会の中のひとつの活動であることを把握すれば、
社会とつながることができると、言い換えることができるでしょう。
―最近、市民に対する科学への理解増進活動が活発になったと感じますが、
その裏には、科学者自身も科学は社会の中のひとつであることを把握すべきという意図もあるのでしょうか?
おそらく表裏一体であると思います。
もちろん一般市民や文系の学生が、「科学技術リテラシー」を身につけることは必要不可欠です。
例えば、原発の話でも、放射能の半減期を知らなければ、賛成も反対もできませんし、
遺伝子組み換え食品の安全性を論ずるのなら、分子生物学の初歩を知らないと、議論にはなりません。
その一方で、科学者や理系の学生が、
自分たちがやっている研究がどういう社会的結果をもたらすかを知らないで、
研究を続けていくのは無責任だし、甚だ危険なことだと思います。
ですから科学者や理系の学生は、科学技術倫理を含んだ「社会文化リテラシー」、
社会や文化の中に自分の研究を位置づけることが必要です。
この「科学技術リテラシー」と「社会文化リテラシー」という二つの流れがうまく噛み合わなければ、
科学と社会を結びつける回路はできてこないのではないでしょうか。
―野家さん、どうもありがとうございました。
コラボレーション
おすすめ記事
 |
【特集】宮城の研究施設 一般公開特集 |
 |
【特集】仙台市総合計画審議会 仙台の10年をつくる |
【科学】科学って、そもそもなんだろう?

若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 【大草 芳江|科学って、そもそもなんだろう?】

地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】

青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 【大草 芳江|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?|防災科学技術研究所】

前田拓人さん(弘前大学)に聞く:<東日本大震災から10年>もし東北地方太平洋沖地震が起きていなければ、地震研究はどうなっていた? 2021.10.08 【大草 芳江|弘前大学|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?】
同じ取材先の記事
◆ 東北大学

地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】

日野亮太さん(東北大学)に聞く:<東日本大震災から10年>もし東北地方太平洋沖地震が起きていなければ、地震研究はどうなっていた? 2021.10.02 【大草 芳江|東北大学|社会って、そもそもなんだろう?|科学って、そもそもなんだろう?】

【レポート】東北大学未来科学技術共同研究センター創立20周年記念講演会/中鉢良治さん(産総研理事長)招待講演「豊かな社会とは?-科学技術の視点から-」 2020.06.05 【大草 芳江|東北大学|科学って、そもそもなんだろう?】
科学って、そもそもなんだろう?
最新5件
 |
若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 |
 |
地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く) 2023.01.26 |
 |
地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 |
 |
「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~ 2022.03.02 |
 |
青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 |
■記事一覧を表示 記事カテゴリ > 科学って、そもそもなんだろう? | |
カテゴリ
取材先一覧
■ 幼・小・中学校
■ 高校
- ・仙台一高 (15)
- ・仙台二華 (14)
- ・仙台二高 (12)
- ・仙台城南高校 (5)
- ・仙台城南高等学校 (0)
- ・仙台高専 (4)
- ・宮城一高 (4)
- ・宮城県高等学校理科研究会 (2)
- ・岩ケ崎高 (1)
- ・東北工業大学高校 (0)
■ 大学
■ 国・独立行政法人
- ・内閣府 (1)
- ・宇宙航空研究開発機構 (5)
- ・文部科学省 (0)
- ・東北経済産業局 (17)
- ・水産総合研究センター東北区水産研究所 (1)
- ・理化学研究所 (3)
- ・産業技術総合研究所東北センター (36)
- ・科学技術振興機構 (1)
- ・防災科学技術研究所 (1)
- ・高エネルギー加速器研究機構 (1)
■ 自治体
- ・仙台市 (8)
- ・仙台市博物館 (4)
- ・仙台市天文台 (12)
- ・仙台市教育委員会 (13)
- ・仙台市産業振興事業団 (1)
- ・仙台市科学館 (8)
- ・仙台文学館 (2)
- ・仙台管区気象台 (2)
- ・塩釜市 (3)
- ・宮城県 (8)
- ・宮城県古川農業試験場 (2)
- ・宮城県教育委員会 (1)
- ・宮城県農業・園芸総合研究所 (1)
- ・気仙沼市 (1)
- ・登米市 (1)
■ 一般企業・団体
- ・DIC株式会社 (2)
- ・K sound design (1)
- ・KDDI (2)
- ・natural science (1)
- ・せんだい・みやぎNPOセンター (2)
- ・てとてと (1)
- ・ひのき進学教室 (11)
- ・みやぎ工業会 (8)
- ・みやぎ工業会会長 (0)
- ・みやぎ産業振興機構 (3)
- ・アスター (1)
- ・インスペック (1)
- ・エツキ (1)
- ・ソニー (3)
- ・ソニー教育財団 (1)
- ・ソフトバンク (1)
- ・ティ・ディ・シー (1)
- ・デュナミス (1)
- ・ドットジェイピー (1)
- ・ナノテム (1)
- ・ハリウコミュニケーションズ (3)
- ・ハード工業有限会社 (1)
- ・フジイコーポレーション (1)
- ・プレファクト株式会社 (1)
- ・ヤマダフーズ (1)
- ・全国学習塾協会 (3)
- ・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (1)
- ・勝山酒造部 (1)
- ・及源鋳造株式会社 (1)
- ・大武・ルート工業 (1)
- ・太白少年少女発明クラブ (1)
- ・宮城の新聞 (0)
- ・宮城県中小企業家同友会 (1)
- ・宮城県産業人クラブ (0)
- ・宮城県職業能力開発協会 (1)
- ・宮城県酒造組合 (2)
- ・工藤電機 (2)
- ・平孝酒造 (1)
- ・応用物理学会 (2)
- ・新東総業株式会社 (1)
- ・日刊工業新聞社 (7)
- ・日本アンドロイドの会 (1)
- ・日本技術士会 (2)
- ・日本私立大学団体連合会 (1)
- ・日本農芸化学会東北支部 (1)
- ・日本IBM (3)
- ・日東イシダ (1)
- ・有限会社 柏崎青果 (1)
- ・東京エレクトロン宮城 (1)
- ・東北ニュービジネス協議会 (1)
- ・東北活性化研究センター (3)
- ・東北経済連合会 (1)
- ・東北電力 (2)
- ・東北電子産業株式会社 (1)
- ・東栄科学産業 (1)
- ・林精器製造 (1)
- ・株式会社三栄機械 (1)
- ・株式会社悠心 (1)
- ・河北新報 (1)
- ・神田産業株式会社 (1)
- ・秋田化学工業 (1)
- ・笹氣出版印刷 (1)
- ・米鶴酒造 (1)
- ・萩野酒造 (1)
- ・農芸化学会 (1)
- ・遠藤工業 (1)
- ・鈴木製作所 (1)
- ・阿部蒲鉾 (1)
- ・阿部蒲鉾店 (1)
- ・鳴子の米プロジェクト (1)
- ・NECトーキン (1)
特別企画 「宮城の塾」
 |
学習塾から見る 宮城の教育の「今」 塾選びに一役 |
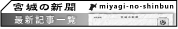
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 若手研究者座談会「地震学×情報科学の融合で得られたもの」 2024.09.16 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く) 2023.01.26 |
 |
【社会って、そもそもなんだろう?】 【同窓生に聞く#01】中鉢良治さん(元ソニー社長、産総研最高顧問)がリアルに感じていることって、何ですか? 2022.10.27 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 地震学×情報科学の融合で、目指すは天気予報の地震版 2022.04.13 |
 |
【社会って、そもそもなんだろう?】 「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~ 2022.03.02 |
 |
【科学って、そもそもなんだろう?】 青井真さん(防災科学技術研究所)に聞く:<東日本大震災から10年>東北地方太平洋沖地震が起きて、地震研究はどう変わった? 2021.11.11 |
記者ブログ

|
ひとり新聞社「宮城の新聞」の大草よしえが衆院選に立候補 2021.10.19 |

|
最近の活動は「Twitter」に移行しました 2019.11.01 |

|
【追記】テレビ朝日「モーニングバード」スタジオ生出演&iCAN'15世界大会(アラスカ)世界第1位! 2015.06.19 |

|
2014年の振り返りと、2015年の抱負 2015.01.05 |

|
平成25年度を振り返りました・・・。 2014.04.02 |
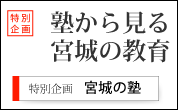
 |
中野塾(泉中央・北高森) |
 |
ひのき進学教室(泉中央・長命ヶ丘・八幡教室・上杉教室) |
 |
夢学館(東照宮・福室) |
 |
早稲田育英ゼミナール(泉中央) |
 |
ソーメック個別学習院(若林区、太白区、泉区に6教室) |
 |
明和塾(北山・八木山) |
 |
JUKU ペガサス仙台南光台教室(南光台南) |
アクセスランキング
- 【宮城の塾】 宮城の塾 仙台市を中心とした学習塾・幼児教室・進学塾の特集
- 世界中の研究者が憧れる研究拠点へ/東北大学WPI-AIMR本館竣工記念式典/科学って、そもそもなんだろう?
- [vol.1] 第1回宮城の日本酒を楽しむ会/社会って、そもそもなんだろう?
- 「仙台の地形と水との関わり」~地形から見る仙台の過去・現在・未来~/社会って、そもそもなんだろう?
- 宮城県仙台第一高等学校/教育って、そもそもなんだろう?
- 【宮城の塾】 ひのき進学教室(泉中央本部教室・八幡町教室・上杉教室・五橋教室・長町教室・愛子教室・吉成教室・大和町教室、他)
- 地震の発生予測に挑む(京大防災研の西村卓也さん・京大名誉教授の平原和朗さんに聞く)/科学って、そもそもなんだろう?
- 【宮城の塾】 JUKU ペガサス仙台南光台教室
- 【宮城の塾】 質問できます!/宮城の塾|宮城の新聞
- 【宮城の塾】 明和塾(北山教室・八木山教室)